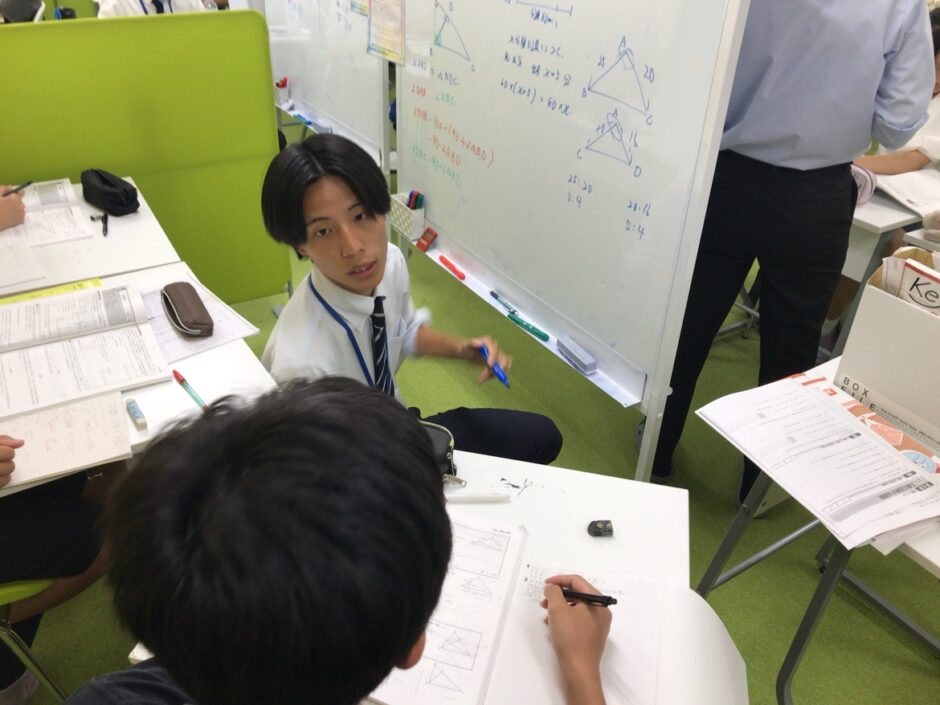こんにちは!高針台中学校前校の南です。
今年も残すところ1か月余りとなりました。
良い年末年始を過ごせるように、12月も頑張っていきましょうね!
さて、今回は「集中」ということについてお伝えしたいと思います。
これを読んでいる塾生のみなさんは普段の塾の授業、学校の授業を集中して取り組めていますか?
みなさんの考える「集中」がどれくらいのレベルか想像しながら以下の話を読んでみてください。
少し昔の本で『武士の娘』という文学作品があります。
作者の杉本鉞子(えつこ)さんは明治の初めに長岡藩(現在の新潟県)の家老の家に生まれ、女性でありながら武士の娘として厳格に育てられた過去を持ちます。
この作品は、江戸時代から明治時代にかけての当時の文化や風俗、人々の価値観が鮮明に描かれており、文化的な価値も高い名著として海外でも有名になりました。
さて、その本の中に次のような一節があります。
《ちょうどお稽古の最中でした。…(中略)…ほんの少し体を傾けて、曲げていた膝を一寸(ちょっと)ゆるめたのです。すると、お師匠さまのお顔にかすかな驚きの表情が浮び、やがて静かに本を閉じ、きびしい態度ながら、やさしく「お嬢さま、そんな気持ちでは勉強はできません。お部屋にひきとって、お考えになられた方がよいと存じます」とおっしゃいました。》
杉本鉞子『武士の娘』大岩美代訳,ちくま文庫,1994年,32頁
これは作者が6歳のときのこと、自宅に僧侶を招き、今でいう家庭教師のような形で勉強をしていた際のエピソードです。
この僧侶は6歳の女の子が少し姿勢を崩しただけで、その日の講義を切り上げてしまったのです。
昔はそれくらい「集中」を大事にしていたのだという表れではないでしょうか。
さて、みなさんは集中していようがいまいが、学校の授業が途中で途切れることはありません。だから、自分が集中できていないことに気付かないでいる可能性が高いのです。
当然、改めようという気も起きません。
そのうち、集中できている人とそうでない人の間に、もはや埋められないほどの差が生まれるのです。
改めて「集中」することの意味を考え、「頭」だけでなく「心」も鍛えましょう。